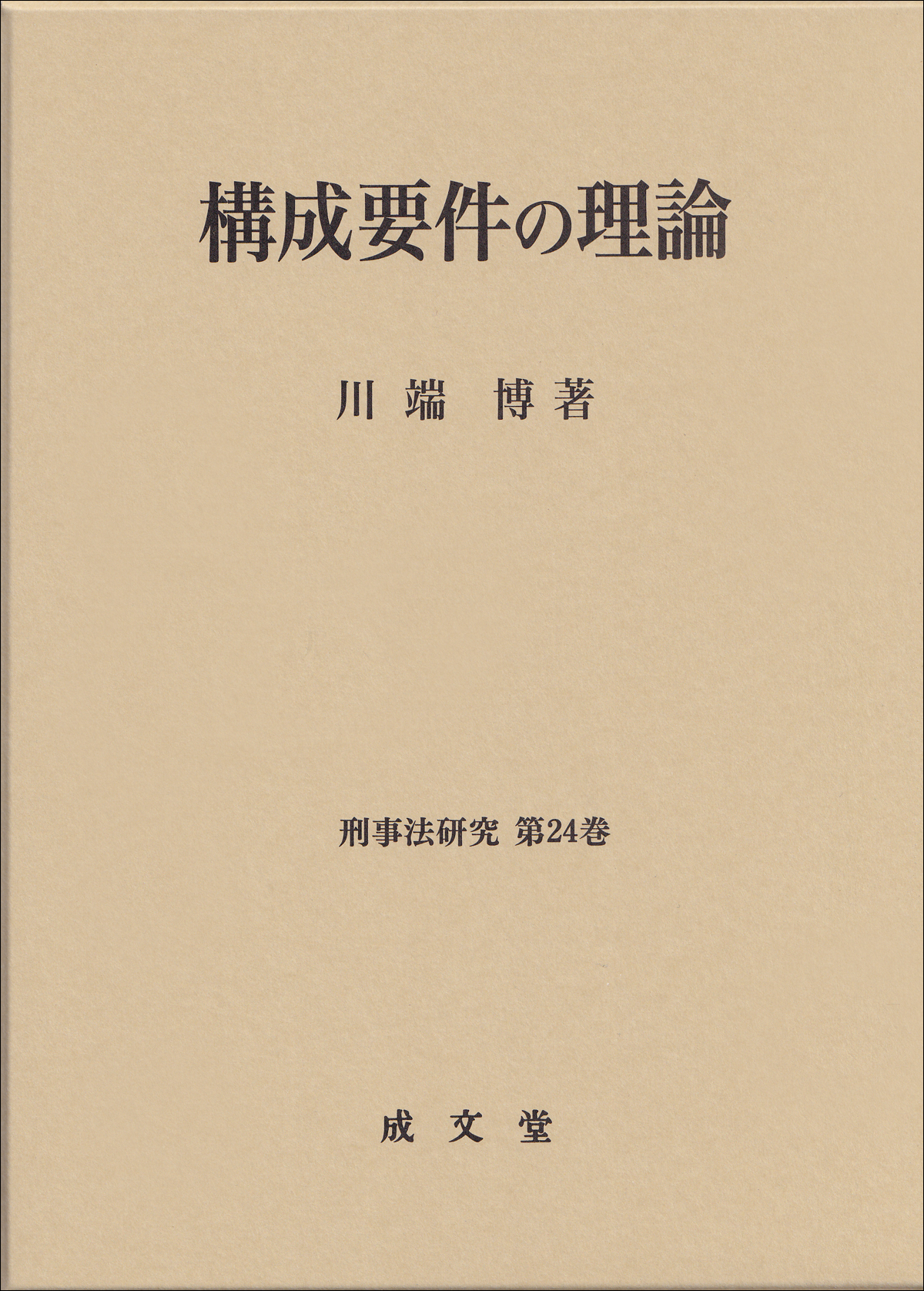
構成要件の理論
川端 博 著
定価:11,000円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2025年07月10日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
480 -
ISBN:
978-4-7923-5448-0
書籍購入は弊社「早稲田正門店インターネット書店」サイトでの購入となります。
《目 次》
はしがき
序章 「構成要件」の理論の問題性 一
第一節 はじめに 一
第二節 構成要件という用語 二
第三節 Tatbestand概念の問題性 四
第四節 構成要件の「機能」 六
第五節 「構成要件」論の射程 九
第一章 ベーリングとその時代の刑法学 一三
第一節 構成要件論の形成前のヨーロッパ刑法学 一三
第一款 刑法思想の発展 一三
第二款 刑法学の発展 一九
第三款 旧派の刑法理論 二六
第二節 ベーリングの構成要件論の生成 三二
第三節 フランスにおける学派の対立 三四
第一款 フランスにおける新旧学派の対立の意義 三四
第二款 古典学派 三六
第三款 新古典学派 四四
第四款 実証学派 四八
第二章 構成要件と法実証主義 五五
第一節 法実証主義の多義性 五五
第一款 問題の所在 五五
第二款 実証主義の基本的特徴 五七
第三款 法実証主義の誕生 五九
第四款 法哲学と実定法との関係 六〇
第五款 法解釈学と法事実学 六三
第六款 広義の法実証主義 六四
第二節 欧米における法実証主義の史的展開 六五
第一款 フランス 六五
第二款 ドイツ 七〇
第三款 イギリス(連合王国) 七八
第四款 アメリカ合衆国 八八
第三節 法実証主義に対する批判 九三
第四節 法実証主義者としての刑法学者達 一〇〇
第一款 フォイエルバッハ 一〇〇
第二款 ビンディング 一〇二
第三款 メルケル 一〇三
第三章 「型」概念と構成要件 一一五
第一節 問題の所在 一一五
第一款 「型」概念の問題性 一一五
第二款 型の文化と知の文化 一二一
第二節 三つの型概念の意義と特質 一三九
第一款 価値型の意義と特質 一三九
第二款 理念型の意義と特質 一四三
第三款 平均型の意義と特質 一五一
第四款 構成要件は何れの型的性質を有するのか 一五六
第五款 総括 一五八
第三節 構成要件と処罰範囲限定機能の根拠 一七八
第一款 問題の視点 一七八
第二款 従来の思想に対するベーリングの影響 一七九
第三款 ベーリングの所説の検討 一八二
第四款 総括―結論 一八八
第四章 翻訳語としての「構成要件」概念 一九七
第一節 問題の所在 一九七
第二節 翻訳の意義 二〇〇
第一款 翻訳と解釈学 二〇〇
第二款 翻訳による優位文化の摂取受容の問題性 二〇二
第三款 翻訳の比較思想的考察 二〇七
第三節 翻訳語としてのTatbestand 二〇八
第一款 問題の所在 二〇八
第二款 Tatbestandの語義 二〇九
第三款 翻訳語の効果 二一〇
第四款 日本語としての「構成要件」の語義 二一三
第五章 規範論と構成要件 二二七
序節 考察の視点 二二七
第一節 ビンディングの規範論の問題性 二二九
第一款 ビンディングの規範論における刑罰法規と規範との関係―制裁法と行為法の視点 二二九
第二款 刑罰法規と一般の法令における罰則との相違―「行為規範の探索」の視点 二三三
第三款 制裁法と行為法の関係―法文の規定形式としての前句と後句の視点 二三五
第四款 規範の実定性―形式的違法性と実質的違法性の視点 二三九
第五款 規範の法源性―立法者による承認の視点 二四二
第六款 ビンディングの規範論と現代の刑法理論―現代刑法理論に対する影響の視点 二四四
第二節 ビンディングの『規範論』とその検討 二五〇
第一款 考察の視点 二五〇
第二款 ビンディング『規範論』の構成 二五一
第三款 ビンディングの規範論の検討 二七四
第三節 ビンディングの規範論がベーリングの構成要件論に及ぼした影響 二八五
第一款 考察の視点 二八五
第二款 ビンディングの規範論の継承 二八六
第三款 ベーリングによるビンディングの規範論の批判点 二八八
第四款 ビンディングおよびベーリングの違法性の観念 二九二
第五款 個別的規範から一般的規範へ 二九五
第六款 ベーリングの構成要件論および規範論の学説史上の意義 二九八
第七款 結語 三〇七
第四節 規範論と構成要件論 三〇七
第一款 考察の視点 三〇七
第二款 規範の意義と規範学 三〇八
第三款 現代の規範論と構成要件論 三二七
第六章 ベーリングの構成要件論 三五七
序説 ベーリング登場までの史的背景 三五七
第一款 スチューベルの刑法思想 三五七
第二款 フォイエルバッハの刑法思想 三五九
第三款 ヘーゲル学派の刑法思想 三六六
第一節 ベーリングの初期の理論 三六八
第一款 学説誕生の背景 三六八
第二款 学説の特徴 三七二
第三款 ベーリングの構成要件論に対する批判 三七八
第二節 後期の理論 三九〇
第一款 論文「構成要件の理論」公刊の背景 三九〇
第二款 「指導形象」としての構成要件概念の提唱 三九三
第三款 「機能概念」としての構成要件への移行 三九九
第四款 ワイマール共和国時代とベーリングの構成要件論 四〇二
第三節 総括 四〇四
終章 わが国における構成要件論の発展と展望 四一三
第一節 考察の視点 四一三
第二節 導入期 四一五
第一款 新旧学派の対立の日本的特徴 四一五
第二款 構成要件論の導入とその検討 四一八
第三節 発展期 四二六
第一款 新旧学派の対立の克服 四二六
第二款 目的的行為論の影響 四二九
第三款 定型説の通説化とその批判 四三三
第四節 構成要件論の現在と展望 四四〇
第一款 現在の問題状況 四四〇
第二款 構成要件の機能 四四一
第三款 違法・責任類型説の検討 四四七
第四款 展望 四五二
事項・外国人名索引 1